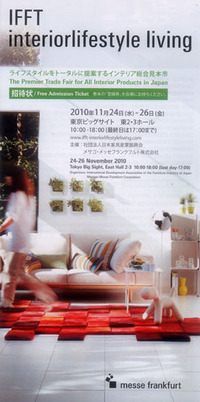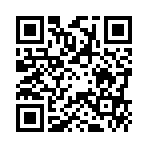2011年02月22日
2月末のゆううつ
展示会が終わって、一段落。
と言ってる場合ではないことが、家にいるとわかる。
考えてみれば(いや、考えるまでもなく)娘の受験まで、
あと10日なわけで。
送られてくるDMの山は、進研ゼミとかZ会とか。
新学年から塾に行くとしても通信添削にするとしても、
いずれも始まるのは3月からだから、
申込み締切まであと数日ってこと。
いやね~~、金のかかる話ばっかり。
子供たちが持って帰ってくるお手紙には、
中学校入学の説明会、とか、
役員やってる委員会の開催、とか、
吹奏楽部卒業記念パーティーのお知らせ、とか、
大事な大事な卒業式のお知らせ(2人分)、とか。
他にも受験日とか発表の日とか、
ええ?いつ?どこ?なに?
覚えとかなきゃいけないことばかりが山盛りで。
仕事に責任を持つ男は大変だと思うけれど(大変だよね?ね?)
時間ごとに頭を切り替えなきゃいけない女も大変(大変なんだよ!)
ご飯のときの義母。
お茶を湯のみに入れて出しても、
ぜったいぜったい食べ終わったお茶碗に淹れ直すの(・_・)
で、そのお茶で茶碗についたお米のぬるぬるをお箸でこすって(・o・)
そのお茶をぐぐーーーーーーーと飲むわけで(ToT)
「こうしたほうが、茶碗洗うのが楽じゃん」って、
そう言われてもねぇ、私にはできませんから!(キッパリ)
いえ、それほどまでに女は忙しいてこと。
ご飯食べるのも茶碗洗うのも同時進行なのよ、昔の人は(あら失礼)
今朝の義母。
まずお茶碗でご飯食べてー、
次にそのお茶碗にヨーグルト入れて食べてー、
そのまた次にお茶碗にお茶淹れてー、
お茶碗のまわりをお箸でぐるぐる~~~~~
で、ぐぐ~~~~~~~~~、ごっくん。
\(゜ロ\)(/ロ゜)/
食べかすも何もかも、飲み干してしまえっていうね。
そうやって生きていくんだなあ、女は。
つまり、女は強しってこと。

と言ってる場合ではないことが、家にいるとわかる。
考えてみれば(いや、考えるまでもなく)娘の受験まで、
あと10日なわけで。
送られてくるDMの山は、進研ゼミとかZ会とか。
新学年から塾に行くとしても通信添削にするとしても、
いずれも始まるのは3月からだから、
申込み締切まであと数日ってこと。
いやね~~、金のかかる話ばっかり。
子供たちが持って帰ってくるお手紙には、
中学校入学の説明会、とか、
役員やってる委員会の開催、とか、
吹奏楽部卒業記念パーティーのお知らせ、とか、
大事な大事な卒業式のお知らせ(2人分)、とか。
他にも受験日とか発表の日とか、
ええ?いつ?どこ?なに?
覚えとかなきゃいけないことばかりが山盛りで。
仕事に責任を持つ男は大変だと思うけれど(大変だよね?ね?)
時間ごとに頭を切り替えなきゃいけない女も大変(大変なんだよ!)
ご飯のときの義母。
お茶を湯のみに入れて出しても、
ぜったいぜったい食べ終わったお茶碗に淹れ直すの(・_・)
で、そのお茶で茶碗についたお米のぬるぬるをお箸でこすって(・o・)
そのお茶をぐぐーーーーーーーと飲むわけで(ToT)
「こうしたほうが、茶碗洗うのが楽じゃん」って、
そう言われてもねぇ、私にはできませんから!(キッパリ)
いえ、それほどまでに女は忙しいてこと。
ご飯食べるのも茶碗洗うのも同時進行なのよ、昔の人は(あら失礼)
今朝の義母。
まずお茶碗でご飯食べてー、
次にそのお茶碗にヨーグルト入れて食べてー、
そのまた次にお茶碗にお茶淹れてー、
お茶碗のまわりをお箸でぐるぐる~~~~~
で、ぐぐ~~~~~~~~~、ごっくん。
\(゜ロ\)(/ロ゜)/
食べかすも何もかも、飲み干してしまえっていうね。
そうやって生きていくんだなあ、女は。
つまり、女は強しってこと。

Posted by フォレストビュー/いちかわ at 09:04│Comments(8)
│日常
この記事へのコメント
お姑さんと、うまくやって下さい。
我が家も同じです。
我が家も同じです。
Posted by kittsan at 2011年02月22日 18:42
at 2011年02月22日 18:42
 at 2011年02月22日 18:42
at 2011年02月22日 18:42*kittsanさん
ジェネレーションギャップと地域性のギャップは埋められませんが、
何とかうまくやっているつもりです。
奥様と話をしたら、盛り上がるかしら~?
ジェネレーションギャップと地域性のギャップは埋められませんが、
何とかうまくやっているつもりです。
奥様と話をしたら、盛り上がるかしら~?
Posted by フォレストビュー/いちかわ at 2011年02月23日 07:49
「もったいない」との日本語が死語に
なりつつある現在ですが、結構同じ事
やっていましたよ皆さん、食糧自給率40%
と言われる我が国、食べ物を粗末にしない
習慣の名残、大事にしたいですね
皆さんでやりましょう義母さんのように。、
なりつつある現在ですが、結構同じ事
やっていましたよ皆さん、食糧自給率40%
と言われる我が国、食べ物を粗末にしない
習慣の名残、大事にしたいですね
皆さんでやりましょう義母さんのように。、
Posted by ワイエス at 2011年02月23日 15:14
さすがにヨーグルトはやらないけど…
みそ汁とご飯が残ると、ご飯にみそ汁を入れてサラサラっと食べたりします。
これを、ブロガーさんの間では有名な「焼津のつかもと食堂」さんでやっもんだから…クマさんに白い目でみられました。
でもいかにもやりそうでしょ、私。(+д+)!!
みそ汁とご飯が残ると、ご飯にみそ汁を入れてサラサラっと食べたりします。
これを、ブロガーさんの間では有名な「焼津のつかもと食堂」さんでやっもんだから…クマさんに白い目でみられました。
でもいかにもやりそうでしょ、私。(+д+)!!
Posted by ゆみ at 2011年02月23日 17:19
*ワイエスさん
私思うんですけど…。
皆が茶碗にお茶を淹れて飲んでても違和感がないって、
静岡の土地柄じゃないかと。
他の地方では、お茶は湯呑に入れるし、
だいいちご飯の最中にがぶがぶお茶を飲まないような。
静岡らしいちゃぁ、静岡らしい習慣です。
私思うんですけど…。
皆が茶碗にお茶を淹れて飲んでても違和感がないって、
静岡の土地柄じゃないかと。
他の地方では、お茶は湯呑に入れるし、
だいいちご飯の最中にがぶがぶお茶を飲まないような。
静岡らしいちゃぁ、静岡らしい習慣です。
Posted by フォレストビュー/いちかわ at 2011年02月23日 21:30
*ゆみさん
ああ~!それ!
次女がね、やるんだけど(それもしょっちゅう)
音まで立てて、ずずーーーって。
「絶対に外でやらないでね!」って言ってます。
ゆみさんは、やるんですね、外で、それもつかもとさん(行ったことないけど)で。
それにしても、ヨーグルトonお茶は、ちょっとドン引きです。
色がね、濁ってるんだもん(泣)
ああ~!それ!
次女がね、やるんだけど(それもしょっちゅう)
音まで立てて、ずずーーーって。
「絶対に外でやらないでね!」って言ってます。
ゆみさんは、やるんですね、外で、それもつかもとさん(行ったことないけど)で。
それにしても、ヨーグルトonお茶は、ちょっとドン引きです。
色がね、濁ってるんだもん(泣)
Posted by フォレストビュー/いちかわ at 2011年02月23日 22:04
再コメント失礼します。
>皆が茶碗にお茶を淹れて飲んでても違和感がないって、
>静岡の土地柄じゃないかと。
その辺りことは詳しく知りませんが、
そういう情景を見たことはあります。
ただ、茶懐石のときの作法と似ています。
実際にわたしも、茶会の食事の終わりにそうしました。
「両碗に湯を注ぎ、飯碗に少量残しておいた飯で湯漬けをする。
香の物は一片を残しておき、これで碗をゆすぐ。
最後は湯を全部飲み切り、器を懐紙で清めて亭主に返す。
これは禅寺の食事作法を取り入れたものである。」
懐石(ウィキペディアより)
以上のように、この習慣は静岡独特のモノでなく、
坊さんの食事のしかたを庶民が真似たのではないでしょうか。
>皆が茶碗にお茶を淹れて飲んでても違和感がないって、
>静岡の土地柄じゃないかと。
その辺りことは詳しく知りませんが、
そういう情景を見たことはあります。
ただ、茶懐石のときの作法と似ています。
実際にわたしも、茶会の食事の終わりにそうしました。
「両碗に湯を注ぎ、飯碗に少量残しておいた飯で湯漬けをする。
香の物は一片を残しておき、これで碗をゆすぐ。
最後は湯を全部飲み切り、器を懐紙で清めて亭主に返す。
これは禅寺の食事作法を取り入れたものである。」
懐石(ウィキペディアより)
以上のように、この習慣は静岡独特のモノでなく、
坊さんの食事のしかたを庶民が真似たのではないでしょうか。
Posted by kittsan at 2011年02月26日 09:28
*kittsanさん
寺の修行僧が、そのようにして食事をするのは知ってます。
茶碗をお湯とたくあんできれいにしたら、
ふき取って膳の中に仕舞って片付けるんですよね。
で、kittsanさんがおっしゃるように、その食事を庶民が真似たのも、そうだと思うんですよ。
で、私が言いたいのはその先でして。
食事時に、お茶が何杯でも飲めるように準備してあるのは、静岡らしいと思うんです。
例えばわたしの実家(横浜)なら、食事が終わって、片付けも済んで、
「お茶でもいかが?」となって、ようやくお茶が出てくる。
お茶はちゃんと嗜好品のお茶として味わうわけで、お水代わりにがぶがぶ飲むのとはちょっと違うんです。
つまり、食事の最後に茶碗でお茶が飲めるようにはセッティングされていないということ。
ということは、寺の坊主のようにマネできるのも、お茶が食事の必須アイテムとして存在する静岡ならではのことかな?と、思ったわけです。
だって、静岡に来たばかりのころ、食事のたびに「お茶淹れた?」って聞かれて、「なんでお茶お茶って、こだわるんだろう?」って思いました。
私は食事のときお茶が無くても普通なんだけど、淹れてないと誰かが「お茶が出てない」って騒ぎ出しますし。
実家の母はダンナに「静岡の人だから、お茶がなくちゃダメなのよね」って言って、お茶を出してます。
他の土地の人は、そこまでお茶生活ではないと思うんですが、いかがでしょうか?
寺の修行僧が、そのようにして食事をするのは知ってます。
茶碗をお湯とたくあんできれいにしたら、
ふき取って膳の中に仕舞って片付けるんですよね。
で、kittsanさんがおっしゃるように、その食事を庶民が真似たのも、そうだと思うんですよ。
で、私が言いたいのはその先でして。
食事時に、お茶が何杯でも飲めるように準備してあるのは、静岡らしいと思うんです。
例えばわたしの実家(横浜)なら、食事が終わって、片付けも済んで、
「お茶でもいかが?」となって、ようやくお茶が出てくる。
お茶はちゃんと嗜好品のお茶として味わうわけで、お水代わりにがぶがぶ飲むのとはちょっと違うんです。
つまり、食事の最後に茶碗でお茶が飲めるようにはセッティングされていないということ。
ということは、寺の坊主のようにマネできるのも、お茶が食事の必須アイテムとして存在する静岡ならではのことかな?と、思ったわけです。
だって、静岡に来たばかりのころ、食事のたびに「お茶淹れた?」って聞かれて、「なんでお茶お茶って、こだわるんだろう?」って思いました。
私は食事のときお茶が無くても普通なんだけど、淹れてないと誰かが「お茶が出てない」って騒ぎ出しますし。
実家の母はダンナに「静岡の人だから、お茶がなくちゃダメなのよね」って言って、お茶を出してます。
他の土地の人は、そこまでお茶生活ではないと思うんですが、いかがでしょうか?
Posted by フォレストビュー/いちかわ at 2011年02月26日 20:45
at 2011年02月26日 20:45
 at 2011年02月26日 20:45
at 2011年02月26日 20:45